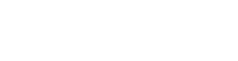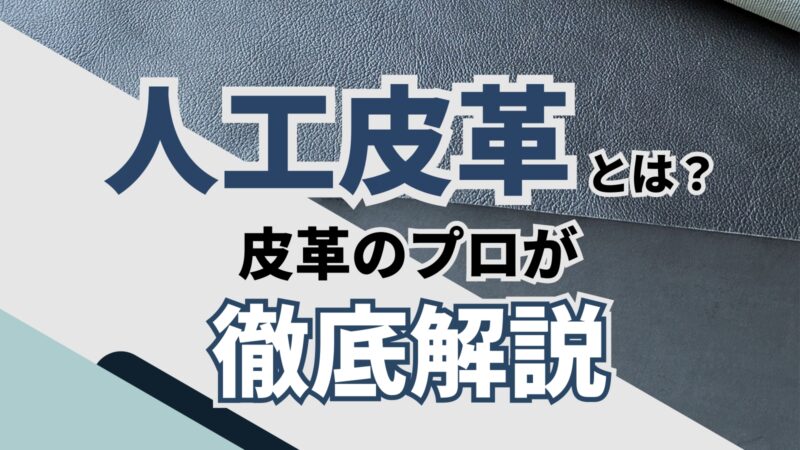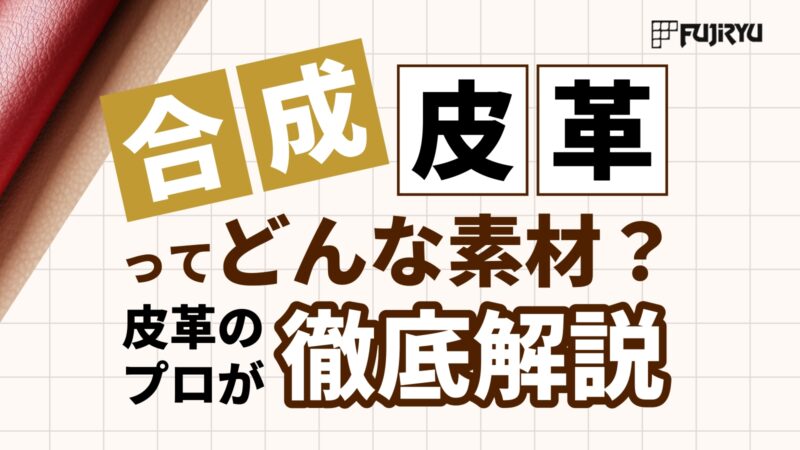鞣し(なめし)とは?|皮が革になるまで
ファッションやインテリアなど様々な製品に使用される素材、革。
本革は動物の皮を使用した素材ですが、素材として使用できるようになるまで必要な工程がいくつかあります。その代表的な工程の一つに「鞣し(なめし)」があります。皮を革へと変えていくための大切な工程、本記事ではそんな鞣しの種類や歴史について解説していきます。
鞣し(なめし)とは?
鞣し(なめし)とは動物の皮を加工し、劣化や腐敗を防ぐことで柔軟性や耐久性を持った素材に仕上げる加工技術です。
加工していない皮は時間と共に腐敗や硬化していきます。そうならない為に、皮の中の脂肪や不純物を取り除き、鞣し剤を浸透させることで皮の繊維層にあるタンパク質を固定、安定化させ、恒久的に使用できる革へと変化します。
鞣しの種類
鞣しの方法も多くありますが、主なものとしてタンニン鞣しとクロム鞣しがあります。また、それぞれの特性を持ったコンビ鞣しという製法もあります。そんな鞣しの種類について解説します。
タンニン鞣し
タンニン鞣しとは植物の幹や樹皮、実や葉に含まれるタンニンを使用した鞣しの方法の一種です。
タンニンはポリフェノールの一種で渋み成分のことを指します。植物が害虫から身を守るために進化の過程で生まれた化合物の一種で、革の鞣しだけでなく、医薬品や食料保存など様々な分野で使用されています。
脱毛、脂肪除去を行った皮にタンニンの溶液を浸すことで革のタンパク繊維を強化します。
タンニン鞣しレザーの特徴
タンニン鞣しで作られた革の最大の特徴は「経年変化」。使い込むほど色つやが変化し、深い色味になります。また、質感もなめらかでやわらかく変化していきます。
経年変化の他にもタンニン鞣しレザーならではの特徴も様々にあります。
・繊維が凝縮し、堅牢で伸びにくい。可塑性(変形させたときに変形したままになる性質)がある。
・植物由来の為、比較的環境負担が少ない。
クロム鞣し
クロム鞣しとは塩基性硫酸クロムなどの化学製品を用いた鞣しの方法の一種です。物騒なネーミングですが、主に人体に無害な三価クロム(必須ミネラル)を使用されています。
革製品の多くはこのクロム鞣しの革を使用しています。
クロム鞣しレザーの特徴
・経年変化が控えめ 経年による変色などが控えめなため、メンテナンスを頻繁に行う必要がないものが多くあります。
・柔軟性、耐水性、耐熱性があり靴、衣料、袋など用途が広い。
・比較的安価 量産しやすいことからタンニン鞣しのレザーと比べ安価です。ですが中にはタンニン鞣しレザーより高価なクロム鞣しレザーもあります。
コンビ鞣し(コンビネーション鞣し)
コンビ鞣し(コンビネーション鞣し)は2つの異なる鞣し方法を掛け合わせた鞣しの方法です。主にクロム鞣しとタンニン鞣しを組み合わせたもののことを言います。
クロム鞣し、タンニン鞣しそれぞれの特徴を持った革で、クロム鞣しの発色性や物性を持ちながらタンニン鞣し特有のコシや経年化を楽しむことができます。
鞣し(なめし)の工程
鞣し(なめし)の工程はタンナーによって違いがありますが、おおよそこの工程に沿って行われています。
準備工程
1.水漬け
屠殺場から輸送された原皮は腐敗が進まないよう塩に漬け込み、脱水された状態になっています。
そんな原皮に付着している血や汚物を取り除き、抜けた水分を補います。
2.裏打ち
フレッシングマシン(裏打機)と呼ばれる機械を用いて原皮に付着している余分な脂肪や肉片を除去します。
3.石灰漬け・脱毛
清潔にさせた原皮を石灰乳に浸漬させ、液に含まれるアルカリによって皮を膨潤させのコラーゲン繊維をほぐし脱毛します。
石灰乳による効果で皮革に柔軟性を持たせることもできます。
4.分割
スプリッティング(分割機)などを用いて、所定の厚さに銀面(表面)と床皮の二層に分割します。
5.垢だし
3の石灰漬け・脱毛の工程で除去しきれなかった毛を垢出機などを用いて除去、銀面を綺麗にします。
7.再石灰漬け
皮をさらに柔らかくする場合は、石灰乳に再度漬け込むことでさらに皮のコラーゲン繊維をほぐし、柔軟性を持たせます。
8.脱灰
石灰漬けの工程で付着した石灰を取り除きます。
9.酵解
酵解(べーチング)することで、不要なタンパク質を分解し銀面を滑らかにします。
鞣し工程
1.浸酸
酸性溶液に浸すことで、革に鞣し剤が均一に浸透しやすい状態にします。
2.鞣し
いよいよ鞣し本番、鞣し剤によって少し工程が変わります。
タンニン鞣し
ピット槽やドラムににタンニン鞣し剤を入れ、じっくり漬け込むことでタンニン鞣しレザー特有の可塑性を与えます。
クロム鞣し
皮にクロム鞣し剤を浸透させ、コラーゲン繊維に結合させます。
3.水絞り
革の余分な水分を水絞り機で絞り出します。
4.シェービング(裏削り)
革製品の用途に応じて、所定の厚みに調整します。
染色工程
1.再鞣し
革製品の用途によって求められる革の性質が異なるため、合成鞣し剤などを使用し再度鞣します。
2.染色
染料を使用し、革に色を付けます。
3.加脂
生油や合成油脂を用いて、革に柔軟性を与えます。
4.伸ばし
サミングと呼ばれる機械を用いて染色した革の水分を取り除くとともに革を伸ばします。
仕上げ工程
1.乾燥
革に染料を定着させるため自然乾燥、熱風乾燥します。
2.革もみ
乾燥した革をステーキングマシンと呼ばれる機械を用いてほぐし、柔らかくする。
3.ガラス張り乾燥・ネット張り乾燥
網や金属板などに革を伸ばしながら乾燥します。
4.縁断ち
不要なフチを裁断する。
5.バフ(ペーパーがけ)
革の種類によっては表面を擦り取ってなめらかにする場合がある。
6.塗装
スプレーや手塗りなどで、着色していきます。
7.アイロン・型押し
革の銀面に艶を出したり伸ばしたりするため、アイロンをかけます。
革に模様をつけるために型を推す場合もあります。
軽量・検査
1.物性検査
革の強度や柔軟性などの品質を検査します。
2.軽量
計量機にかけて革の面積を測ります。国内では主にデシという単位で取引され、10cm×10cmを1デシと計算されます。
鞣しの歴史
人間は地球上で生存を始め、狩猟によって生活を営んでいた時代から動物の皮を使用してきました。防寒着やテントと用途は様々で、鞣しの技術は古代エジプトから生まれていたとされています。
19世紀にはクロム鞣しが登場、現在では高級ブランドで使用されるほどポピュラーな革になりました。
まとめ
いかがでしたでしょうか?皮は長い工程を経て革へと変化していきます。
その工程の多さ、技術をよく知ることで革を育てる楽しみ、使う楽しみが増していきます。
ぜひ革製品を使う際、革の製法について思い出してみてください。